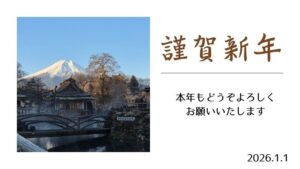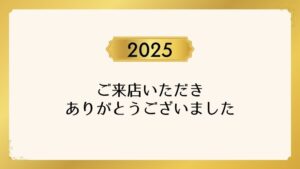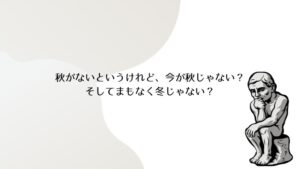こんにちは!名古屋市名東区のフラット鍼灸院の院長の山田です!
寒い季節から暖かくそして暑い季節になるにつれてお酒好きの方はついつい冷たいお酒の量が増えがちなではないですか?
そこで!
「楽しくビールなどのお酒はたくさん飲めるけれど、同じ量の水を飲めと言われたら・・・絶対飲めない」
「お酒なら飲めるのに水を同じだけ飲めと言われると絶対飲めないのなんでだろう??」
こんな疑問を抱いたことはありませんか?
よく施術中に皆様との会話の中でも話題になることありますよね?なんでだろうね~、と真相にたどり着けず終わってしまっていましたが・・・
今回ついに調べてみました!
諸説あるようですが、わかったことをまとめてみました。興味のある方、最後まで読んでみてください♪
水はたくさん飲むと満腹感を感じる理由

水はたくさん飲むと満腹感を感じます。だれしもが見ずに限らず水分をたくさん飲んでお腹が一廃になった経験があるかと思います。
そもそも水は純粋な液体です。そのため胃に入るとすぐに「胃が膨らんだ」と感じさせ、満腹中枢を刺激します。
つまり、ただただ胃が水で満たされていてお腹いっぱいの状態です。
たくさん飲んでもお酒だと感じにくい理由
水はたくさん飲むと満腹になるものの、お酒だと満腹感を感じにくい理由は、アルコールの持つ
- 胃の動きを促進する
- 麻痺効果で満腹感が鈍る
- 脳の報酬系を刺激する
作用が大きく関わっています。
胃の動きを促進するとは?
ビールやワインなどのアルコール飲料は、少量のアルコールが胃の動き、蠕動運動(ぜんどううんどう)を促進します。
簡単に言うとアルコールには胃の中身を腸に早く送り出す作用があります。そのため胃が満たされにくい感覚になり、たくさん飲めてしまいます。
麻痺効果で「満腹感」が鈍るとは?
アルコールには中枢神経を麻痺させる作用があります。
その影響で、本来感じるはずの満腹感や飲みすぎ感が鈍くなり、気づかないうちにどんどん飲んでしまうことがあります。
脳の報酬系を刺激するとは?
アルコールは脳の報酬系を刺激し、快感を感じる神経伝達物質(ドーパミンなど)を分泌させます。
その結果、身体が満たされているかどうかより、「もっと欲しい」という心理的な欲求が優先されがちになります。

生存に必要な行動(食事、性行動など)を繰り返し行わせるための神経回路です。
この回路は、行動によって得られる快感(ドーパミンの放出)を介して、行動を促します。
加えて
ビールなどの炭酸入りのお酒は口当たりが爽やかで、飲むことが自体が快感になります。
プラスαとしてお酒を飲む環境、場面などの心理的な側面です。
食事や宴会、会話中はリラックスしていて食欲や満腹感に対する意識が薄れ気づいた時にはたくさん飲んでしまっている、ということに。

水とお酒(アルコール)の特徴のまとめ

水とお酒(アルコール)で満腹感のでやすさや神経への影響などを簡単にまとめました。
| 特徴 | 水 | アルコール(ビールなど) |
|---|---|---|
| 満腹感の出やすさ | 出やすい(胃がすぐ膨れる) | 出にくい(胃の動き促進) |
| 神経への作用 | なし | 中枢を鈍らせる・快感を与える |
| 飲みごたえ | 単調・飽きやすい | 味・香り・炭酸で変化がある |
| 心理的効果 | 少ない | リラックス・快楽がある |
最後に
お酒(アルコール)を飲んで陽気になっている人を見たことが誰しもあるはず。
その姿を見てきっとお酒は脳に何らかの影響があるんだろうな~と薄々は気づいていたと思います。
まさに、脳を刺激し、心地よい状態へ導くよう作用するのがお酒です。
楽しくお酒を楽しむポイントは周りや、ご自身の健康に悪影響が出ない範囲で理性を保てる範囲内での飲酒が望ましいですね!
たくさん飲めるから飲めるだけ飲む・・・という飲み方は気をつけましょう!